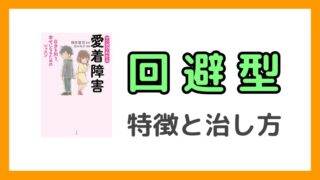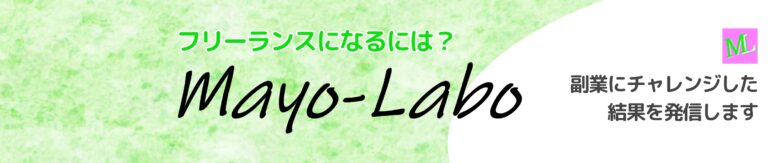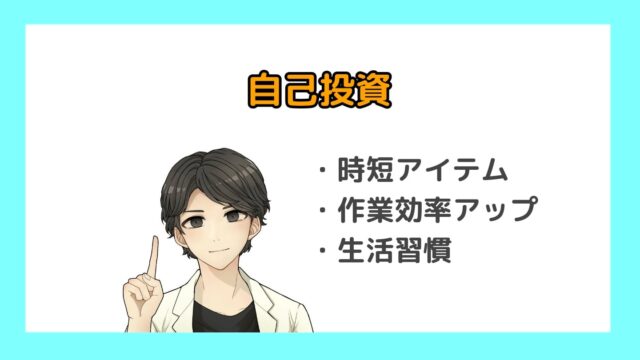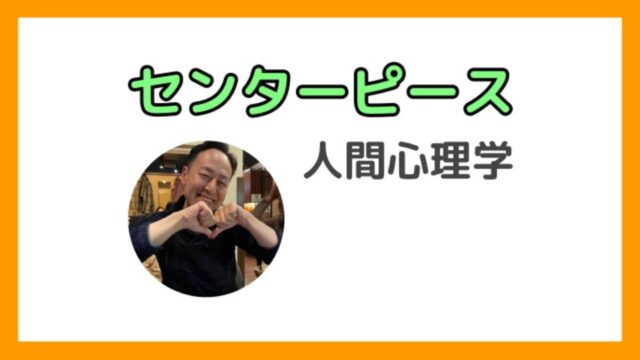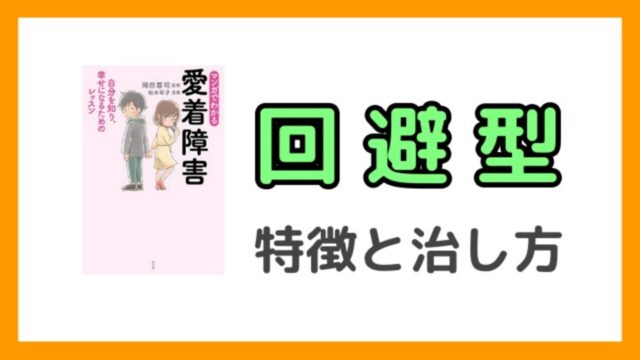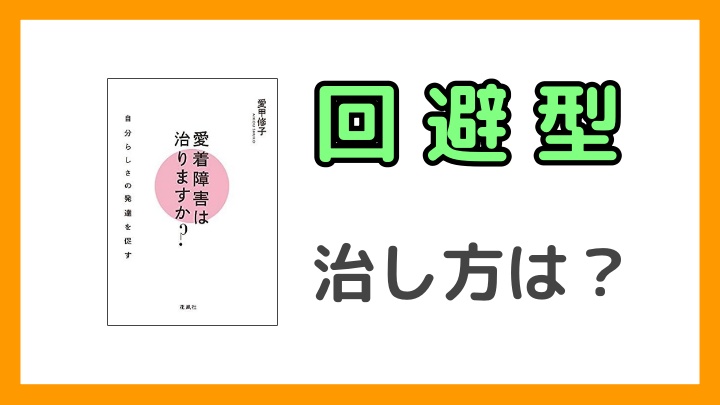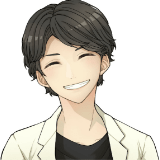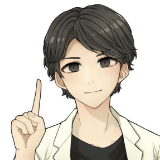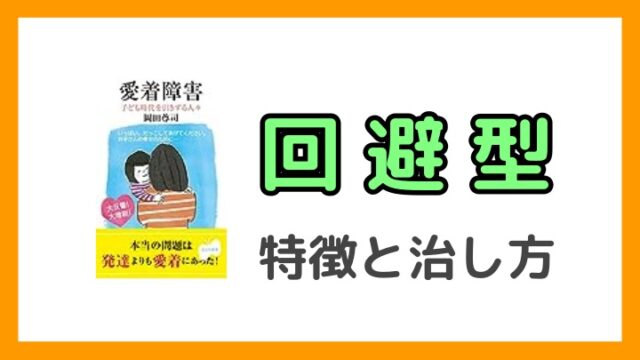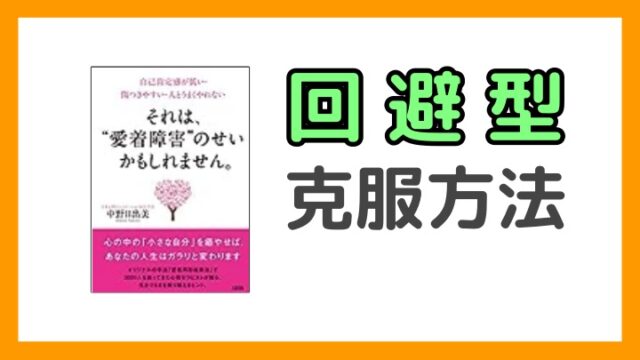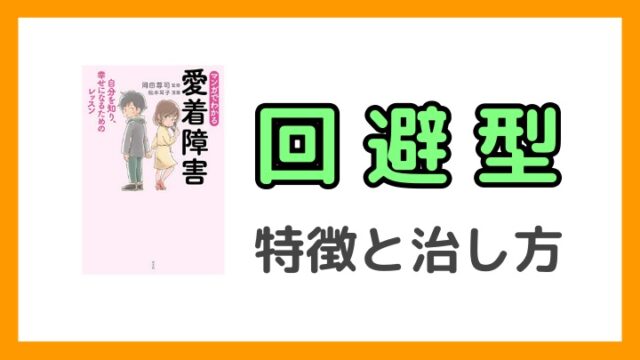- 自分の意見をはっきりさせない生き方をしている
- 人との交流を心から楽しめない。
- 社会に対して、被害者的な意識がある
このような、「回避型の愛着スタイル」を持つ方へ向けての記事です。
こんにちは、回避型スタイルを自負するマヨネです。
自分が回避型だと気づいても「じゃあ、いったいどうすれば良いのか」を、疑問に感じる方も多いと思います。
そこで今回は、書籍『愛着障害は治りますか?』の中から、「回避型の人に期待できる治し方」をお届けします。
ずばり、本書で書かれている回避型愛着障害の治し方は、下記の3つです。
- 子どもの頃を思い出し、言葉にする
- 体の背面をゆるめる
- 自分にとっての快不快を追求する
それぞれの詳しい内容と、「回避型ならではの特徴」や「子供の行動」も分かりやすくまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
書籍『愛着障害は治りますか?』の簡単な紹介
2016年に発行された本で、著者は臨床心理士・言語聴覚士の愛甲修子(あいこうしゅうこ)さんです。
著者:愛甲修子
千葉大学大学院教育学研究科修士課程修了。
精神科医の神田橋條治氏と日本臨床心理士会会長の村瀬嘉代子氏に師事し、愛着障害は治ることを実践し実証している。
淑徳大学総合福祉学部非常勤講師と、国立木更津工業高等専門学校学生相談室カウンセラーを務める。
本書で語られている内容がこちらです。
『愛着障害は治りますか?』の主な内容
- 愛着障害とはどのようなものか
- 愛着障害に手遅れはない
- 愛着障害を治す方法
- なぜ愛着障害を治すべきなのか
治し方は?(『愛着障害は治りますか?』の本より)
本書で紹介されている愛着障害の治し方は、下記3つです。
- 子どもの頃を思い出し、言葉にする
- 体の背面をゆるめる
- 自分にとっての快不快を追求する
子どもの頃を思い出し、言葉にする
言葉を通して、子供の頃の「温かさや匂い、体感」などをイメージすることが、愛着障害の解消へとつながります。
子どもの頃のトラウマを抱えている人たちは、言葉にならない不全感を抱えたままになっているからです。
とはいえ、どうやって子どもの頃を思い出せばよいのか、疑問ですよね。
「子どもの頃を思い出す3つの方法」が、こちらです。
子どもの頃を思い出す3つの方法
- フォーカシング
- 内観法
- 「懐かしさ」を感じる時間を取る
フォーカシング
フォーカシングでは「自分がどう感じているのか」に焦点を合わせ、感覚を言葉にしていきます。
アメリカの哲学者で臨床心理学者の、ユージン・ジェンドリンが開発した心理療法です。
フォーカシングのやり方がこちらです。
- 落ち着く空間で深呼吸をする
- 「子どもの頃に、気がかりになっていることは何だろう?」と自分に問いかけてみる
- 「説明できないモヤモヤした体の感覚」が出るまで待つ
- 出てきた「モヤモヤした体の感覚」の中から、焦点をあてたいものを1つ選ぶ
- 「モヤモヤした体の感覚」にぴったりな言葉を表現してみる
- 言葉が「モヤモヤした体の感覚」のイメージとぴったりか、感じ合わせてみる
- 「そのモヤモヤした体の感覚は、何を伝えに来ているのか?」と自分に問いかけてみる
- 「モヤモヤした体の感覚」を、ただ感じてみる
参考図書:『マンガで学ぶフォーカシング入門―からだをとおして自分の気持ちに気づく方法』より
内観法
内観法は「身近な人に対して、自分とのかかわり」を見つめ直していきます。
僧侶の吉本伊信(よしもといしん)によって開発された自己観法です。
内観法のやり方がこちらです。
まず、小学校低学年にさかのぼります。
そこから年代順に身近な人(父母、祖父母、兄弟、姉妹、配偶者)に対して下記3つ、具体的なエピソードを思い出していきます。
思い出す身近な人とのエピソード3つ
- していただいたこと
- して返したこと
- 迷惑をかけたこと
「懐かしさ」を感じる時間を取る
「懐かしさ」は子供の頃の体験と深くつながってるため、記憶をたどるヒントになります。
1人ひとり、過去の体験は異なり、五感の感じ方も違うはずです。
あなたが「懐かしさ」や「ワクワクした思い出」をより感じることに、時間を取ってみましょう。
記憶をたどるきっかけになる行動7つ
- 森林浴
- 海水浴
- 座禅
- 音楽ざんまい
- 旅行
- 名作にふれる
- 親におんぶしてもらう
体の背面をゆるめる
母親のおなかの中にいるときの外部ストレス(胎児期の愛着障害)には、「体の背面をゆるめる」アプローチが有効です。
自分を守るときに、胎児のときは背中を丸めて固める姿勢をとっていたからです。
仰向けで背骨をゆらゆらさせる「金魚運動」や、「整体」を受けに行くのがよいです。
自分にとっての快不快を追求する
自分の快不快を分かるように心がけていくと、愛着の問題は消えていきます。
回避型の人は、社会に対して「他人の都合に合わせなければいけない世界」と考えがちです。
「ルールを守ること」を「自分を抑えること」と、とらえているからです。
自分にとっての快不快を追求し、、自分の価値観をはっきりさせていく。
そうすると、親や他者の顔色をうかがうことが減っていきます。
回避型かもしれない子供の行動(『愛着障害は治りますか?』の本より)
本書に記されている愛着障害の子どもの行動の中でも、回避型の可能性がある行動がこちらの2つです。
- 抱っこを嫌がる
- 2~4歳の反抗期がない
抱っこを嫌がる
愛着障害のある子は、0~5歳の乳幼児期に抱っこされることを嫌がる傾向にある。
2~4歳の反抗期がない
愛着障害のある子は、2~4歳頃にあるといわれている第一次反抗期がない傾向にある。
読んだ感想:回避型うんぬん関係なく、自分の価値観が大切
回避型の僕は、「自分をはっきりさせない生き方」を「自らの戦略として選んでいたんだ」と、改めて感じました。
なぜ自分をはっきりさせない生き方を選んだかというと、人の顔色が気になるから。
自分の本音を隠してがまんした方が、いざこざを避けられる。
ハッ! がまんするストレスを避けるために、人付き合いを減らせば良いんだ。
1人でいるのが楽だ。
そうだ! 「そもそも1人でいるのが好きだ」という設定にしておこう。
こうして回避型から抜け出せれなく、なっていたのだと思います。
そこで、本書で紹介されている
- 『マンガで学ぶフォーカシング入門』著者:福盛英明、森川友子
- 『改訂 精神科養生のコツ』著者:神田橋條治
を読んで、回避型の克服に取り組み始めました。
まだ取り組んでいる最中ではありますが、気づきがたくさんあります。
「自分の価値観をはっきりさせていくことは、回避型うんぬん関係なく、良いことにつながりそうだ」
ちぐはぐな人生を送っていた自分に、気づきを与えてくれる1冊となったのは、まちがいないです。
まとめ:自分の本当の気持ちを取り戻したい!
本書で紹介されている愛着障害の治し方は、下記の3つです。
- 子どもの頃を思い出し、言葉にする
- 体の背面をゆるめる
- 自分にとっての快不快を追求する
「自分の意見をはっきりさせるのに抵抗がある」や「社会を他人の都合に合わせる場」に感じてしまう方の、お役に立てると嬉しいです。
僕も、回避型愛着とずっと付き合っていくものとして、養生に励んでいます。
他にも回避型愛着障害について良い情報がありましたら、ぜひ教えて下さい。